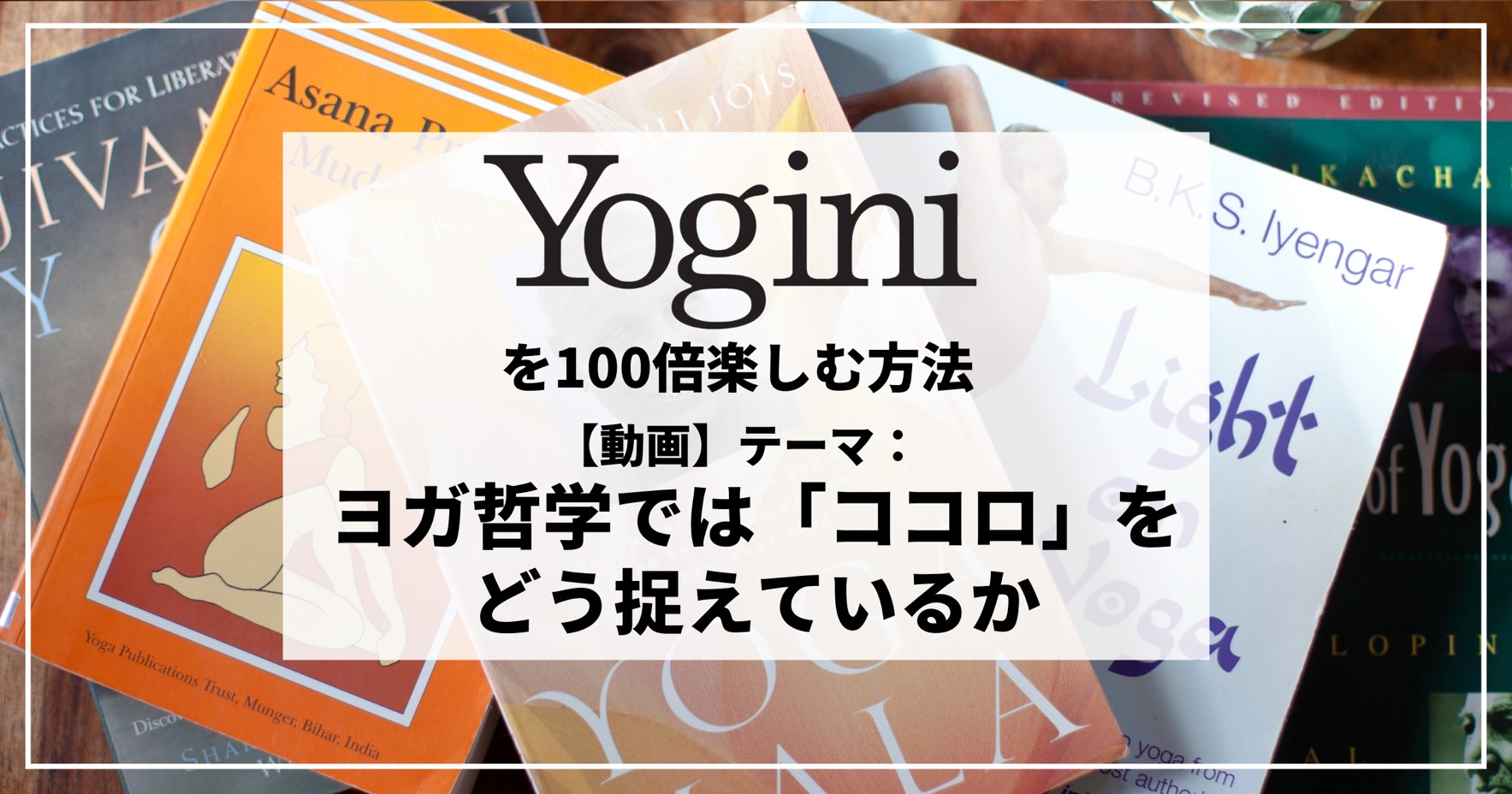
【動画】ヨガ哲学でココロはどう伝えられているのか。
ヨガはココロを扱う
ヨガはココロを扱うメソッドだ。体を動かアーサナ(ポーズ)にしても、哲学にしても、瞑想にしてもターゲットになっているのは、ココロ。揺れ動き、扱いにくい、時に扱いきれないココロをどうにかコントロール下に入れたい、という古代からの人々の思いが、ヨガを体系づけていったとも言えるのではないだろうか。
ココロを分類、分析
ヨガはココロをターゲットにした。だから、ココロについて知る必要があった。自分達はどんな相手と向き合おうとしているのか。ココロって何? 何をしているところ? どんな種類があって、質があって…。そのために、ヨガの哲学ではココロを定義し、分類し、分析した。
しかし、ヨガの哲学がまとまったのは、はるか昔。しかも、そもそもはサンスクリット。古来、たくさんの人が解釈を試みて、解説本があるものの、比喩や省いている言葉なども多く、増して体験しないことにはわからない部分もたくさんあるために、ココロを理解するのはなかなか難しい。
ヨガ哲学、心理学の側面から解説
ということで、ヨガの先人である西川眞知子先生にヨガ哲学で説明する「ココロ」を話してもらった。『ヨーガスートラ』だけでなく、『ウパニシャド』なども含めて解説し、広く捉えているために、全体感を捉えるにはとてもわかりやすい。
西川先生の話は『Yogini』Vol.83「五つの苦悩との向き合い方」、さらに、別冊アーカイブ『ヨガを深く学びたい!』に掲載された(初出典は『Yogini』Vol.71)の記事をも基に解説している。続けて聞くとわかりやすい。Yoga Wikiの「心 さまざまな定義づけによってひもとかれてきたヨガのターゲット」という記事も合わせて読んでみて。
西川眞知子先生の配信はこちら。
また、現代の心理学の面からもココロの話をしている。
稲富正治先生の配信はこちら。
Profile:西川眞知子
にしかわまちこ。ヨガとアーユルヴェーダの融合をテーマに執筆や講師活動を行う。インテグラルヨガの創始者スワミ・サッチダーナンダ氏に学ぶ。著書は『ヨガのポ ーズの意味と理論がわかる本』他 多数。https://www.jnhc.co.jp
